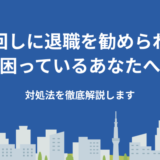適応障害を理由に仕事を辞める人が増えています。
この障害は、職場や家庭など様々なストレスが原因で起こり、うつ病と間違えられることもありますが、環境を変えることで改善する場合もあります。
適応障害の発症者は増加傾向にあり、即日退職が可能な場合もあれば、手続きに時間がかかる場合もあります。退職する際は、医師から診断書をもらい、上司や会社に正式に手続きを行うことが大切です。
また、退職後は傷病手当金や失業保険などの支援制度を利用することができます。適応障害で悩んでいる場合、ハローワークや精神保健福祉センターなどで相談することが推奨されます。

適応障害を理由に辞めてもいい?

適応障害で辞めるときの注意点はある?
辞めるまでの流れがわからない…
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
適応障害で働ける状態にない方の中には、すぐにでも退職したいと考えている方もいるでしょう。
結論、適応障害を理由に即日退職することは可能で、流れや注意点などを理解しておくのがポイントです。
今回は、適応障害を理由に辞める方法や流れ、注意点、利用できる制度などを解説します。
最後まで読めば、適応障害で辞める方法や流れなど、疑問に感じていることを解消できるでしょう。

退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。
今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!
- 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
- 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
- 最短1ヶ月で受給可能!
- 最大200万円の受給ケースあり!

失業保険全般の相談も受け付けています
適応障害で仕事を辞めてもよい

適応障害を始めとする精神疾患が原因で辞める人は増える傾向にあり、以下の特徴があります。
- 適応障害を発症する原因
- 適応障害を発症する社会人の数
- 適応障害で即日退職できる可能性もある
ここから具体的に解説します。
適応障害を発症する原因
適応障害になる原因は、会社や家庭、恋愛、病気などから受けるストレスで、受けたストレスに対して適切な対応ができないことから発生するとされています。
うつ病と間違えられるケースもあるものの、居場所が変わると症状が改善したり、医師と前向きに話し合えたりする傾向にある点は異なります。
外国の場合、夫婦間のストレスや経済問題などを理由に、ストレスを抱える人が多い傾向にあります。
日本の場合、職場の人間関係や仕事内容などに対して、ストレスを抱える人が多い傾向にあるのが特徴です。
適応障害を発症すると、不安感を強く感じたり対人トラブルが起こりやすくなったりすることから、働き続けることが難しくなります。
出勤すると動機や息切れを起こすようになるケースもあるなど、適切な対応をしないと症状は悪化します。
体調に異変を感じた場合、なるべく早く専門機関を受診するのが一つの方法です。
適応障害を発症する社会人の数
厚生労働省の発表により、適応障害を発症する社会人の方は増え続ける傾向にあることが判明しました。
2008年には約4万人であったものの、2017年には2倍以上となる約10万人の方が適応障害を発症しています。
適応障害に限りませんが、近年では精神疾患になる方が増える傾向にあることから、他人事だとは考えないことが望ましいです。
厚生労働省が令和2年に実施した調査によると、精神疾患の患者は419万3,000人いることがわかっています。
ストレスを自覚している方は特に、働き方や生活習慣などを見直し、病気を発症する前にストレスを緩和させることがポイントです。
適応障害で即日退職できる可能性もある
適応障害を発症した場合、即日退職できるケースと退職するまでに期間を要するケースにわけられます。
即日退職するには、止むを得ない事情であることが会社に認められる必要があり、具体的には以下の2つです。
- 体調不良であること
- 親の介護をする必要があること
適応障害を始めとする精神疾患は目に見えないことから、医療機関を受診したうえで診断書をもらっておくと即日退職しやすくなるでしょう。
即日退職できない場合でも、法律では2週間前に申告すればよいとされており、退職日まで無理に出勤する必要はありません。
有給を消化したり安静に過ごしたりしながら、退職日を迎えましょう。
適応障害で仕事を辞めるまでの流れ

適応障害で辞めるときは、手順を押さえておくことでスムーズに辞めやすくなるでしょう。
- 病院で診断書を発行してもらう
- 上司に退職の意思を伝える
- 会社の規則に則り手続きをする
- 同僚に挨拶する
上記の点について、ここから具体的に解説します。
病院で診断書を発行してもらう
適応障害で会社を辞めるときは、病院で診断書をもらうとよいでしょう。
適応障害を理由に会社を辞められるものの、診断書があると説得力が増すためです。
会社によっては診断書の提出を求められるケースもあることから、事前に診断書をもらっておくとスムーズに辞めやすいといえます。
診断書は医療機関に依頼することで作成してもらえ、診断書作成料として3,000円から5,000円程度の料金が発生します。
即日作成してもらえるケースもありますが、一般的に2週間程度の期間が必要であることから、早めに依頼しておくのが望ましいです。
上司に退職の意思を伝える
病院で診断書の作成を依頼したあとは、会社を辞めたい意思を上司に伝えましょう。
退職理由については、適応障害であることを伝えるのが理想的ではあるものの、「一身上の都合」や「健康上の理由で」としても問題にはなりません。
上司との関係性に応じて、伝えやすい理由を選ぶのがポイントです。
上司に伝えるときは、なるべく落ち着いて話しができるように、以下の通りタイミングにも気を配るのが望ましいです。
- 出勤前
- お昼休みが終わる前
- 就業後
上司に直接伝える方がよいものの、体調が悪くて出勤できない場合や話し合える環境にない場合は、メールや電話、LINE、退職届の郵送などの手段を使うとよいでしょう。
人によってはマナー違反だと捉えられる恐れがあるものの、法律上は問題ありません。
会社の規則に則り手続きをする
上司に退職の意志を伝えたあとは、会社の規則に則って退職の手続きを進めるとスムーズに退職できるでしょう。
会社によっては、退職届のフォーマットが用意されているケースもあることから、確認しておくのが望ましいです。
就業規則では、退職日の1ヶ月前までに申告することを決めているケースが多く、なるべく早く退職の意思を伝えることが理想的です。
適応障害の方の場合、健康状態を理由にすぐにでもやめたいケースもあるでしょう。
前述の通り、即日会社を辞める方法もあることから、自分の置かれている状況に応じてどうするのかを決定するのがポイントです。
同僚に挨拶する
退職申請を進めたあとは、同僚の方に感謝の気持ちを伝えてから辞めましょう。
会社に出勤できる体調の場合、お菓子を持参して挨拶をするとより感謝の気持ちを伝えやすくなります。
会社の大きさにもよりますが、小分けされているお菓子を選ぶと分けやすく便利です。
社員証やカードキーなど、会社から借りている備品を返却することもポイントです。
適応障害の方の場合、体調によっては無理に出勤して挨拶する必要がないことは理解しておくとよいでしょう。
適応障害で仕事を辞めるときの注意点
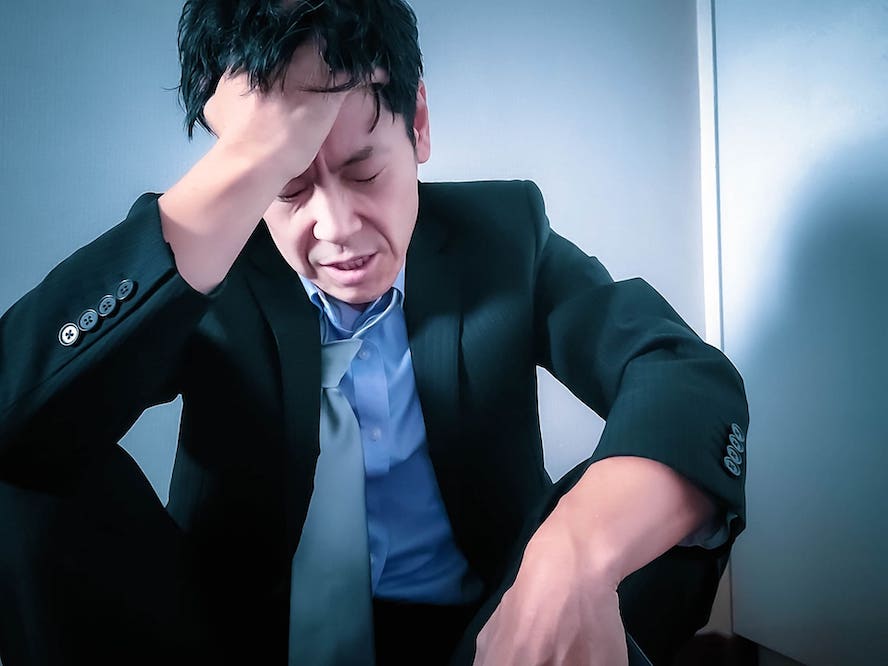
適応障害で仕事を辞めるときは、退職したあとに後悔するのを防ぐうえでも以下の注意点を押さえておくのが望ましいです。
- 状況に応じて退職代行を使う
- 有休を消化する
- 退職せず休職を検討する
- 上司に相談する
ここから具体的に解説します。
状況に応じて退職代行を使う
適応障害を理由に退職することを会社に言い出せなかったり、スムーズに辞められない状況にあったりする場合は退職代行を利用するとよいでしょう。
退職代行とは、自分のかわりに退職の意思を伝えてくれたり、有給休暇の取得の交渉などをしてくれたりするサービスであるためです。
費用が発生するものの、退職するときに必要なことは全て任せられることから、会社とトラブルが発生している方や関係性が良くない方など、さまざまな状況にある方が利用する傾向にあります。
退職代行サービスは会社によって内容や費用が異なることから、比較検討したうえで利用するのがポイントです。
有休を消化する
適応障害で退職するときは、残っている有給を全て消化してから辞めるのがポイントです。
有給を消化することに罪悪感を感じる方もいるかも知れませんが、有給の消化は労働者の権利として法律で認められており、原則として自由に取得が可能です。
有給が残っている方の場合、退職の意志を告げてから退職日までの期間を有給消化に当てるとよいでしょう。
有給を使い切らずに会社を辞めても、その分の費用は支払われない点は注意が必要です。
退職せず休職を検討する
適応障害で会社を辞める前には、休職して体調が回復するのを待つのも一つの方法です。
健康状態が悪いと正常な判断をできなくなる可能性があり、回復してから「やっぱり会社を辞めなければよかった」となる事態を防ぐためです。
適応障害の原因はストレスであるケースが多いことから、原因となっているストレスから6ヶ月間離れることで改善するといわれています。
休職すれば治療に専念できたり、自分と向き合う時間を十分に確保できたりすることがメリットです。
上司に相談する
適応障害で会社を辞める前には、上司に対して辞めない方向で相談するのも一つの方法です。
勤めている会社の人間関係や仕事内容に関して特別な不満がない場合は特に、継続して勤務する方法を模索できると理想的です。
仕事を通してストレスを感じにくくするのがポイントで、上司に相談するときは以下の点を押さえるとよいでしょう。
- 部署異動させてもらう
- 時短勤務にしてもらう
- 雇用形態を変えてもらう
- リモートワークにしてもらう
- 勤務日数を減らしてもらう
- 転勤させてもらう
会社の都合にも合わせながら、お互いにとって最善の方法を模索するのが望ましいです。
適応障害で仕事を辞めるときに利用できる制度・手当

適応障害で仕事を辞めるときは、条件を満たせば以下の制度や手当などを利用できる可能性があり、生活面を安定させやすくなるでしょう。
- 傷病手当金
- 失業保険
- 自立支援医療制度
- 就労移行支援
- 障害年金
- 生活保護
ここから具体的に解説します。
傷病手当金
適応障害が原因で仕事をやめる方は、傷病手当金をもらえる可能性があります。
傷病手当金とは、適応障害を始めとする精神的な病気やけがなどにより、仕事を長期間休まざるを得ないにも関わらず、会社から十分な給料をもらえない場合にもらえるお金のことです。
傷病手当金をもらうには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガが原因での休職であること
- 仕事をできない状態であること
- 「連続する3日」を含み4日以上出勤していないこと
- 休業しているときの給料が支払われない、または十分に支払われないこと
適応障害を発症した方の場合、傷病手当金ではなく労災保険による休業補償等給付の対象となるケースもあります。
失業保険
適応障害で仕事を辞める方は、条件を満たせば失業保険をもらえます。
失業保険とは退職した方が再就職するまでの生活面のサポートを目的とするもので、退職理由や雇用保険に加入していた期間などに応じてもらえる金額は変わります。
適応障害を理由に退職となった場合は「特定理由離職者」として扱ってもらえることから、もらえる金額や入金までの期間などで優遇を受けられます。
自立支援医療制度
適応障害で仕事を辞める方は、自立支援医療制度を利用できる可能性があります。
自立支援医療制度とは、適応障害を始めとする精神疾患を理由に通院する必要がある場合、医療費の一部を軽減してもらえるのが特徴です。
自治体によって異なるものの、原則として医療費は1割のみ負担すればよくなります。
世帯の総所得額などに応じて、負担上限月額を設けている点は注意が必要です。
就労移行支援
適応障害で仕事を辞める方は、就労移行支援を利用できる可能性があります。
就労移行支援とは、病気や障害を持っている方が、一般企業で就職したり継続して働き続けることをサポートする施設であるためです。
適応障害だと医師から診断されている方の場合、0円で利用できるケースもあります。
就労移行支援を利用できるかは各自治体によって個別にチェックされるのが特徴です。
障害年金
適応障害で仕事を辞める方は障害年金を利用できる可能性があります。
障害年金とは、病気などが原因で仕事に支障を来している場合に年金の加入者がもらえるもので、若い世代も対象となるためです。
ただし、適応障害のみでは障害年金をもらう対象とならず、原則として障害認定日に障害等級1等から3等のいずれかに該当する必要があります。
生活保護
適応障害で仕事を辞める方は、生活保護をもらえる可能性があります。
生活保護とは、病気やケガなどが原因で働けない方や、働いても十分な給料を得られない方などが最低限の生活をできるようにサポートする制度です。
生活保護を受けられれば、生活費や医療費、再就職するうえで必要な訓練費用などの支援を受けられます。
適応障害で仕事を辞めたい人が利用したい機関

適応障害で仕事を辞めたいと考えているときは、以下の期間や団体などで相談することができます。
- ハローワーク
- 精神保健福祉センター
- 基幹相談支援センター
- 労働条件相談ほっとライン
- 法テラス
- 総合労働相談センター
ここから具体的に解説します。
ハローワーク
適応障害で仕事を辞めたいと考えているときは、ハローワークを利用するとよいでしょう。
ハローワークでは、適応障害などの病気を患っている方に向けた求職情報の提供や相談などを行っているためです。
障害者手帳がなくても利用できるのが特徴で、専門の相談員の方から一貫したサポートを受けられます。
精神保健福祉センター
適応障害で仕事を辞めたい方は、精神保健福祉センターを利用するのが一つの方法です。
精神保健福祉センターとは、適応障害を始めとするこころの病気に関する相談や医療機関の情報提供、社会復帰の支援などのサポートを行っている施設です。
センターにもよりますが、医師や臨床心理士などの専門家がいるケースもあり、仕事の悩みに関する相談が可能です。
基幹相談支援センター
適応障害で仕事を辞めたいと考えている方は、基幹相談支援センターを利用するとよいでしょう。
基幹相談支援センターとは、主に障害がある方の生活サポートをすることが目的の施設で、病院や学校など地域にある施設と連携をとっています。
適応障害を経験している方の生活面の相談にものってもらえることから、退職したいことに関して適切なアドバイスをもらえる可能性は高いです。
労働条件相談ほっとライン
適応障害で仕事を辞めたい方は、労働条件相談ほっとラインを利用するのが一つの方法です。
労働条件相談ほっとラインとは、違法な労働時間や過酷な労働環境による健康障害などに関して相談できる電話相談窓口です。
誰でも無料で利用できるのが特徴で、専門知識を持つ相談員の方に対して匿名で気軽に相談できます。
法テラス
適応障害で仕事を辞めたい方は法テラスを利用するとよいでしょう。
法テラスでは、弁護士や司法書士の方から以下の2つのサービスを受けられるためです。
- 無料相談:法律問題に関して、1回あたり30分程度の相談を最大で3回まで受けられる
- 民事法律扶助:経済的な余裕のない方が弁護士や司法書士に問題の解決を依頼する場合、費用を立て替え払いしてもらえる
法テラスを利用する場合、一般的に法律事務所などに比べると費用を抑えやすい点が特徴です。
総合労働相談センター
適応障害で仕事を辞めたい方は、総合労働相談センターを利用するとよいでしょう。
総合労働センターとは、労働局や労働基準監督署などにある窓口のことで、パワハラや解雇など仕事に関する問題や悩みなどの相談に乗ってもらえるのが特徴です。
法令違反の可能性が高い場合、労働基準監督署に引き継いでもらえるなど、解決に向けてサポートしてもらえます。
まとめ
適応障害を理由に仕事を辞める方法や流れ、利用できる手当などを解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 適応障害で仕事を辞めることは可能で、即日退職できるケースもある
- 適応障害で仕事を辞めるときは流れ通りに進めることで、スムーズに辞めやすくなる
- 適応障害で仕事を辞めるときの注意点として、有給を全て消化したり退職せずに休職を検討したりする点があげられる
- 適応障害で退職する場合、条件を満たせば傷病手当金や失業保険などの制度や手当を利用できる
- 適応障害で辞めるとき、悩みやトラブルなどが発生している場合はハローワークや精神保健福祉センターなどを利用できる
適応障害とはストレスが原因の病気であることから、仕事から離れて体調回復を優先させるのがポイントです。
会社を辞める判断は重要なものであることから、休職し体調回復してから決断するのも一つの方法です。
本記事を参考に、適応障害を発症したときに仕事を辞める方法や注意点、利用できる制度などを理解していただければ幸いです。